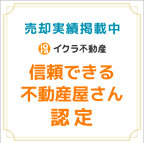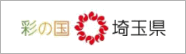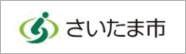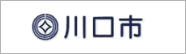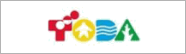さまざまな事情により、所有している空き家の管理が適切に行えていない持ち主の方が増えています。その場合、各市区町村が空き家の実態を調査・把握し、何らかの対策を取っていくことになります。今後の対策を検討するにあたり、また適正な措置を図るため、空き家の実態を調査している自治体もあります。調査報告書は開示されていますが、実際に読んだことのある方は少ないかもしれません。そこで今回は「埼玉県の空き家実態調査」をとりあげ、内容を読み解いていきます。
埼玉県空家実態調査: https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/akiya-chousa.html
・調査概要
平成23年11月1日時点での県全域における賃貸用住宅や、二次的住宅等を対象とし、居住実態の調査を行っています。空き家の判定基準については、以下のとおりです。
1)電気メーターが動いていない
2)郵便受けに大量の郵便、チラシがたまっている
3)近隣住民からの情報
4)外観が廃屋風で、人が住んでいる気配がない
5)その他
・カーテン、表札がなく、雨戸を締め切っている。
・建物周囲に入居者募集中や空き家の案内看板がある。
・調査結果
埼玉県が調査した空き家実態調査と、国が行った「平成20年度住宅・土地統計調査」を比較したものが以下の内容です。母数は異なるものの、増加傾向にあることがわかります。
埼玉県の調査
調査対象数:79,944 …(1)
空き家数:8,890 …(2)
空き家率:11.1 …(2)/(1)×100
平成20年度住宅・土地統計調査
調査対象数:3,029,000 …(1)
空き家数:322,600 …(2)
空き家率:10.7 …(2)/(1)×100
・空き家の現状
空き家の問題点としてよく挙げられるのは、建物の老朽化がもたらす周辺への影響です。倒壊や災害の危険、または衛生上の問題が懸念されます。実際、今回の調査でも空き家の2割に何らかの問題がみられ、そのうち半数は外観上で腐朽や破損が確認できたそうです。
これは、長期間空き家になっている建物が増えていることも要因のひとつといえそうです。空き家になってからの年数が1年以上3年未満が29.6%、3年以上が12.5%となっています。特に戸建て住宅は空き家年数3年以上が41.2%に及んでいます。
空き家になった理由としては「相続での取得」「所有者の転居」などが挙げられ、その後活用できていないというケースが多いようです。その結果、定期的な点検も入居者の募集も行っていない状態の空き家も一定数あることが伺えます。
・最後に
購入者も入居者も募集していない一戸建てが5割以上あり、さらに活用方法も決まっていないものが約5割存在しています。自治体でも空き家対策に取り組んでいますが、あくまで決定権は所有者の方にあります。空き家の所有者の中には「どうしたらいいかわからない」という方もいるため、どんな活用方法があり、具体的にどのようなアクションを起こすべきかが広く知られる必要があるのかもしれません。

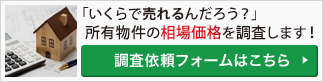
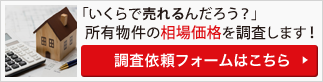









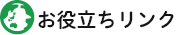

 不動産売却するならドットコム
不動産売却するならドットコム