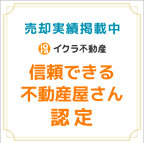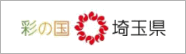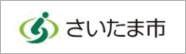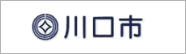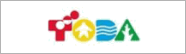「空き家を有効活用したいが、どうすればよいか分からない」「賃貸住宅として貸し出すためにリノベーションしたいが、法的な知識に自信がない」そうした不安を抱える空き家所有者は少なくありません。
近年、日本全国で空き家の数は増加傾向にあり、社会問題としても注目されています。維持管理にかかる固定資産税や草木の管理費用、倒壊などによる近隣トラブルの懸念など、「持っているだけ」で負担となる空き家。これを収益化する手段の一つとして注目されているのが、「賃貸住宅としての再生・リノベーション」です。
しかし、空き家をリノベーションして第三者に貸し出すには、避けて通れない大きなハードルがあります。それが「建築基準法」です。
建築基準法とは、建物の安全性・衛生面・防災性などを担保するために設けられた法律で、賃貸住宅のように第三者が住む用途に転用する際には、より厳格な基準が適用されます。違反すれば、是正命令や罰則、最悪の場合は使用停止になることもあります。
本記事では、空き家を賃貸住宅にリノベーションする際に知っておくべき建築基準法の基礎から、2025年の法改正による影響、リスクの回避方法まで解説します。
参考:賃貸住宅のリノベーションにおいてなぜ建築基準法が重要なのか?
https://albalink.co.jp/realestate/vacant-house-definition/
参考:ルールを守らないと罰則もある
https://www.j-reform.com/publish/pdf/re-tebiki2021.pdf
建築基準法の基本とリノベーションへの適用
建築基準法とは?
空き家を賃貸住宅へと転用する際に最初に直面するのが、「建築基準法」の壁です。空き家を賃貸住宅に転用する際には、まず建築基準法の基本的な内容を理解することが重要です。建築基準法は、建物の安全性・衛生・防火性・居住性などを守るための最低限のルールを定めた法律で、日本国内で建築物を建てる、改築する、用途変更する際には、原則としてこの法律に従う必要があります。
建築基準法の目的は、「人の生命・健康・財産の保護」と「都市の健全な発展」にあります。つまり、リノベーションによって見た目を美しくし、空間を快適に整えるだけでは不十分で、構造的な安全性や住環境としての適切さが法的に担保されていることが前提となるのです。例えば、建物が接道義務を満たしているか、耐震性能が確保されているか、防火や採光、換気の条件を満たしているかといった点がチェックされます。建物の建築年や構造、立地によって適用される具体的な基準は異なりますが、これらを理解していないままリノベーションを進めると、法令違反により是正命令が出されたり、最悪の場合は使用停止を命じられたりすることもあります。
特に賃貸住宅として第三者に貸し出す場合には、自宅用よりも高い基準が適用されると考えてよいでしょう。なぜなら、不特定多数の人が入れ替わりで住む可能性があるため、一定の安全・衛生水準を満たすことが求められるからです。
建築確認申請が必要となる工事
建築確認とは
リノベーションに取りかかる前に必ず行いたいのが、「この工事は建築確認申請が必要かどうか」の判断です。建築確認とは、工事内容が建築基準法などの法令に適合しているかを、自治体または指定確認検査機関が事前に審査・許可する制度です。
確認申請は、通常は建築士などの専門家を通じて行われます。書類の作成、図面の提出、役所や確認検査機関とのやり取りが発生するため、許可が下りるまでには1〜2か月程度かかることもあります。一見すると、外装を変えない「軽微なリノベーション」であれば申請は不要と思われがちですが、内部の構造や用途に関係する工事は意外と申請対象となることが多いため、必ず事前に確認が必要です。
建築確認申請が必要なリノベーションとは
空き家を賃貸住宅にリノベーションする際、すべての工事が自由に行えるわけではありません。一定の規模や内容の工事については、建築確認申請が必要になります。これは、建物が建築基準法に適合しているかを事前に行政や指定確認検査機関がチェックする手続きです。
以下に、建築確認申請が必要とされる代表的な4つのケースを解説します。
大規模な修繕
「大規模な修繕」とは、建物の構造部分(柱・梁・壁・床など)にわたる大がかりな補修工事を指します。特に建物の延べ面積の1/2を超えるような構造的な修繕を行う場合には、原則として確認申請が必要です。
大規模の模様替
「大規模の模様替」は、建物の主要構造部に影響を及ぼすような内装変更を指します。こちらも延べ面積の1/2以上にわたる変更が目安です。
用途変更
「用途変更」とは、建物の使用目的を変えることを指します。たとえば、空き家として使っていた建物を、賃貸アパートやシェアハウス、事務所などに変更する場合が該当します。用途の変更によって建築基準法上の規定が変わるため、確認申請が必要になります。
増築
「増築」は、建物に新たな床面積を加える工事です。たとえば、既存の平屋に2階部分を増築したり、離れや新たな部屋を建て増しするなどが該当します。規模の大小にかかわらず、原則として確認申請が求められます。
2025年建築基準法改正による影響
2025年4月から建築基準法が改正され、省エネ基準の適合義務化と構造安全基準の見直しが行われます。これは新築のみならず、増築や大規模なリフォームも対象となるもので、空き家の再生計画に大きな影響を及ぼす重要な改正です。
特に注意すべき点は、この新たな基準が「建築確認済証の取得日」ではなく、「工事の着工日」を基準に適用されるという点です。たとえば、2025年3月に建築確認を取得していたとしても、実際の工事の開始が4月1日以降であれば、新しい省エネ基準および構造基準が適用されるという仕組みです。これは、リノベーションの準備が整っていても、資材調達の遅れや天候による着工延期など、些細なスケジュールのズレが直接的に設計や費用に影響することを意味します。したがって、建築確認の取得だけで安心せず、「着工日」まで見据えたスケジュール設計が、今後の計画立案においてますます重要になってきます。
参考:https://www.zoukaichiku.com/kaisei202412
省エネ基準が厳しくなった
これまで努力義務とされていた断熱性能や一次エネルギー消費量の基準が、改正により新築・増築・大規模改修のいずれにおいても原則適合義務となりました。たとえば、外壁、屋根、床の断熱材の仕様、窓の断熱性、給湯・冷暖房・照明などのエネルギー消費設備の性能について、所定の基準を満たす必要があります。
構造のチェックが厳しくなった
これまで木造住宅では適用除外とされていた一部の建築物に対しても、構造計算の義務化が進められます。具体的には、高さ16m以下であっても3階建ての木造建築物や、一定規模以上の建物については、許容応力度設計や保有水平耐力計算などの高度な構造計算を要するようになります。これにより、設計段階から専門的な知識を有する建築士の関与が必要不可欠となり、費用や設計期間にも影響を与える可能性があります。
参考:https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf
参考:https://www.zoukaichiku.com/kaisei202412
求められる住宅の性能
リノベーションの実施にあたっては、耐震性能、火災安全性、採光・換気、シックハウス対策といった基本的な住宅性能の確認も不可欠です。
災害に対する安全性
● 耐震性能
1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅では、耐震診断と補強工事が推奨されます。
国土交通省の発表した耐震化の進捗状況によると、平成20年時点の耐震化率は、住宅が約79%、 多数の者が利用する建築物が約80%となっています。
引用:https://www.taishin-jsda.jp/column.html
● 火災
火災安全性では、火災警報器の設置や防火建材の使用が求められ、特に準防火地域・防火地域では建材の仕様に制限があります。
引用:https://tateel.jp/column/ap62/
引用:https://www.seiwa-stss.jp/tochikatsuyo/knowledge03/k03cat04/8.html#section_toc-7
● 採光・換気・シックハウス
各居室での開口部の面積や換気量に関する基準があり、これらが不足していると、賃貸住宅として認可されない可能性もあります。さらに、ホルムアルデヒドをはじめとした揮発性有機化合物への対策、いわゆる「シックハウス症候群」対策として、建材の使用が基本とされます。
これらの省エネ性能・構造安全性・住環境に関する基準を総合的に把握し、事前に専門家と調整を行うことで、無駄な設計変更やコスト増加を避け、確実に建築確認を取得することができます。従来よりも詳細な耐震性能の確保が必要になるため、工事費用や設計コストの増加も見込まれます。
引用:https://chintai-kanrishi.com/chintaikanrishi-commentary/building/building-standards-law/
古い家(既存不適格)のリノベーションには注意が必要
古い空き家の中には、「既存不適格建築物」と呼ばれる建物が多く存在します。これは、建築当時には合法であったが、その後の法改正により現行の基準には適合しなくなった建物を指します。この種の建物は、現状のまま使用し続けること自体には問題ありませんが、大規模な修繕や用途変更、増築を行う場合には、建物全体を現行基準に適合させなければならなくなります。
例えば、接道義務を満たしていない物件に対して増築を行うと、その建物全体が違法建築とみなされ、工事の中止や是正命令を受ける可能性があります。そのため、空き家を活用する前に、自身の所有する建物が既存不適格に該当するかどうかを確認することが重要です。
確認方法としては、建築確認済証や検査済証の有無、建築計画概要書などの行政書類を取得し、建築士とともに内容を精査するのが一般的です。また、用途地域や建ぺい率・容積率の確認も合わせて行い、どこまでの改修が可能かを事前に明確にしておく必要があります。
既存不適格であることが判明した場合でも、リフォームの範囲を調整する、使用用途を変更せずに賃貸に出すなど、柔軟な対応によって活用は十分に可能です。重要なのは、「法律に違反しない形で、どこまでできるか」を見極めることになります。
建築確認の流れ
リノベーションに際して建築確認申請が必要となる場合、その手続きの流れをあらかじめ把握しておくことで、スムーズに計画を進めることができます。一般的な建築確認申請のプロセスは以下のようになります。
まず、建築士に依頼し、現地調査と設計図の作成を行います。ここでは、耐震性や断熱性、防火性などの基準を満たす設計が求められます。その後、設計図と必要書類を添えて、所管の建築主事または指定確認検査機関に申請を行います。申請後、1週間から2か月程度の審査期間を経て、確認済証が発行されれば工事に着手することが可能となります。
工事が完了した際には、完了検査を受け、「検査済証」が発行されて初めて建物の使用が認められます。これらのプロセスを踏まずにリフォームを進めた場合、違法建築と判断される可能性があり、後々の賃貸契約や売却にも大きな影響を与えかねません。
手続きにかかる費用は規模や内容によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が一般的になります。
参考:https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/kenchikukakunin/
迷ったらプロに相談しましょう
建築基準法を正しく理解し、それに基づいたリノベーションを実現するためには、建築や法律の専門家との連携が不可欠です。空き家を賃貸住宅として再生させる取り組みは、個人にとっては資産活用の一環であり、社会全体にとっても空き家問題の解決に貢献する意義深いものです。しかしながら、建築基準法をはじめとした各種法令に適合させることが絶対条件となります。自己判断で進めた結果、法律に抵触してしまったケースは少なくなく、プロのアドバイスを得ることが最も確実な方法と言えます。
たとえば、建築士は法令に即した設計や構造計算、省エネ基準の適合確認などを担い、建築確認申請のサポートもしてくれます。また、行政書士や司法書士は契約関係や補助金申請などの法務手続きを支援してくれます。工務店は、実際の施工計画を立案し、工程管理を行います。不動産会社は賃貸市場のニーズや家賃設定、広告戦略についてのアドバイスを提供してくれるでしょう。
これらの専門家を組み合わせてチームを作ることで、リノベーション計画が格段にスムーズに進みます。特に初めて空き家を活用するオーナーにとっては、信頼できるパートナーの存在が成功のカギを握ると言っても過言ではありません。まずは現地調査と法的制限の確認からスタートし、信頼できるパートナーと共に、安心・安全・快適な賃貸住宅づくりを進めていきましょう。

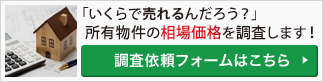
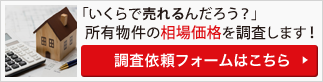








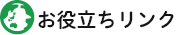

 不動産売却するならドットコム
不動産売却するならドットコム