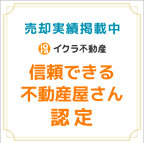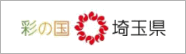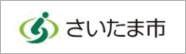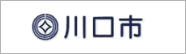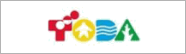「空き家を持っているけれど、どう活用したらいいかわからない」「リフォームしないと借り手がつかないけれど、大きな費用はかけられない」というお悩みをお持ちではないでしょうか。日本全国で増え続ける空き家問題。所有していても維持費や固定資産税だけがかかり、なかなか手がつけられないという方は多くいらっしゃいます。賃貸に出したいけれど、リフォームや修繕に大きな費用をかけるのはためらわれる。そんな悩みを解決する手段の一つが、「DIY可能な賃貸物件」という選択肢です。
DIY可能な賃貸物件とは、入居者が自由に内装や設備を手直しできる物件のことです。一般的な賃貸物件では「原状回復義務」があるため、退去時には元通りにしなければなりません。しかし、DIY可能物件では、入居者が自らリフォームやカスタマイズを行い、自分好みの空間を作り上げることが認められています。これにより、オーナー側は大規模なリフォーム費用をかける必要がないのです。
このスタイルは、リフォーム費用を抑えたいオーナーと、理想の住まいを手に入れたい入居者の双方にとって魅力的な仕組みですが、その一方で注意すべきポイントもあります。本記事では、DIY可能な賃貸物件の概要や、オーナー・入居者双方のメリット、成功のための注意点、実例まで詳しく解説します。
DIY可能な賃貸物件とは?
DIY可能な賃貸物件とは、入居者が内装や設備を自由に手直しできる賃貸物件です。通常の賃貸住宅では、退去時に原状回復を求められ、壁紙の張替えや床材の変更などは基本的に禁止されています。しかし、DIY可能な物件では、入居中に入居者が自ら好きなようにリフォームを行うことができ、退去時にもその状態を維持するか、部分的な回復で済ませる契約になっていることが多いのが特徴です。
このDIY可能な賃貸借は、空き家問題の解決策として国も推進しています。2013年、国土交通省は「DIY型賃貸借」という新たな賃貸経営方法を提案し、「DIY型賃貸借契約」の雛形を公開しました。この制度は、深刻化する日本の空き家問題の解決策として注目されており、オーナーと入居者の双方に新たな選択肢を提供しています。
参考:https://www.homemate.co.jp/chintai-article/diy/005/
国もDIY型賃貸借を推進している
DIY可能な賃貸物件のメリット
オーナー側のメリット
オーナー側のメリットとして、大掛かりなリフォーム工事をしなくて済むため、初期コストを大幅に抑えられることが挙げられます。一般的な賃貸物件では、入居者募集の前にリフォームや修繕を行い、内装をきれいに整える必要があります。しかし、DIY可能な賃貸物件では、「現状渡し」が基本となるため、オーナー自身が大きなリフォーム費用を負担する必要はありません。これにより、空き家活用の初期コストを大幅に抑えることができ、資金的な負担が軽減されます。
入居者が自分で手を入れることで愛着が生まれ、長く住んでもらえる傾向もある
入居者が自分の手で内装を整えることで、その物件に対する愛着や満足感が生まれやすくなります。この心理的効果によって、長期間住み続けてもらえる傾向があり、空室リスクの低減にもつながります。特にDIY好きな方やクリエイティブなライフスタイルを求める層にとって、自由に手を加えられる住まいは大きな魅力です。
競合物件との差別化
「現状渡しでもOK」「DIY歓迎」といった特徴は他にない付加価値
DIY可能な物件は、一般的な賃貸物件とは異なる層の入居者、例えば若年層やクリエイティブ志向の方、あるいはデザイナーや建築関係者など、空間作りに関心がある層に訴求できます。この層は賃料よりも自由度や個性の表現を重視する傾向があり、安定的な賃貸運用につながる可能性があります。
物件価値の向上
入居者が退去する際に、DIYで施した内装を残していくことを契約で合意しておけば、結果的にオーナー様の費用負担なしに物件の価値が向上する可能性も考えられます。
管理業務の軽減
DIY可能な賃貸物件では、入居者が自ら内装のメンテナンスや修繕を行うため、日常的な管理業務の負担が軽減されることがあります。もちろん、建物本体の維持管理や法的な修繕義務はオーナーにありますが、内装や設備に関する細かい対応が減ることで、管理の手間が減少することが期待できます。
入居者側のメリット
自分好みの住空間を実現できる
最大の魅力は、自分好みの空間を自由に作れることです。一般的な賃貸物件では、内装や設備を変更することが禁止されている場合がほとんどですが、DIY可能な物件では、壁紙の張り替えやペンキ塗り、棚の取り付けなどが自由に行えます。
これは、クリエイティブな空間作りを楽しみたい人にとって大きな魅力です。たとえば、「北欧風にまとめたい」「インダストリアルな雰囲気にしたい」「和モダンを取り入れたい」など、自分のライフスタイルに合わせたデザインが可能です。さらに、自ら手を加えることで、愛着が湧きやすく、居心地の良い住まいになります。
比較的賃料が割安な可能性がある
DIY可能な賃貸物件は、リフォーム前の状態で貸し出されることが多いため、周辺相場よりも賃料が割安に設定されるケースがあります。オーナーはリフォーム費用をかけずに貸し出すため、その分賃料を抑えられるのです。
たとえば、同じエリアの一般的な賃貸物件が月10万円程度でも、DIY可能物件では7〜8万円といった形で提供されることがあります。その分、入居者自身がリフォーム費用を負担する必要がありますが、自由度とコストのバランスを取りながら、自分らしい暮らしを実現できるのは大きなメリットです。
退去時に原状回復がいらない可能性が高い
一般的な賃貸物件では、退去時に壁紙を元に戻したり、取り付けた設備を撤去したりと、原状回復義務が発生します。しかし、DIY可能な物件では、契約によってその義務が免除されていることが多く、退去時の費用や手間がかからないのも魅力です。
もちろん、オーナーと事前にどこまで原状回復が必要かを取り決めておくことは重要ですが、DIYで手を加えた部分をそのまま残して退去できる場合が多いです。これにより、入居者は自分の好みに合わせた空間作りを存分に楽しむことができます。
DIY賃貸を成功させるポイント
住居に必要な安全性と機能性の確保
最初に取り組むべきは、物件の安全性と基本機能の確保です。DIY可能だからといって、何も手を加えずそのまま貸し出してよいわけではありません。住宅として最低限必要な部分は、オーナー側の責任で修繕・整備しておく必要があります。
長期間空き家だった物件では、屋根や外壁の劣化が進んでいることが多く、目視では気づきにくい小さな雨漏りが存在しているケースもあります。DIYで壁紙や内装をきれいに整えたとしても、雨漏りが発生すればカビや腐朽が進行し、結果として入居者満足度が大きく低下します。入居後のトラブルを避けるためにも、屋根や外壁のチェックを専門業者に依頼し、必要な修繕を行いましょう。
特に古い物件では、配管や電気設備の老朽化も見逃せません。配管の詰まりや漏水は、住宅トラブルの上位に位置する問題です。これを放置して貸し出すと、入居後にトラブルが発生し、オーナーが修繕費用を負担することになります。これも専門の水道業者や電気業者による事前点検と必要な修繕が欠かせません。
また、給湯器やガスコンロなどの設備が残っている場合、動作確認と安全性のチェックも行いましょう。特にガス設備に不備があると、命に関わる事故につながる可能性もあります。給湯器やガス設備は、必要に応じて交換や修理を行うことが求められます。
清掃は徹底的に実施
物件の安全性や機能性が確保できたら、次に行うべきは徹底した清掃です。DIY可能物件だからといって、ホコリや汚れが目立つ状態で募集をかけると、入居希望者は「手を加える前に掃除が大変そうだ」と感じ、敬遠されることがあります。むしろ、清潔な状態だからこそ、DIYのイメージが膨らむものです。
DIY賃貸でも第一印象が重要です。たとえば、カビやホコリが残ったキッチンを見ると、それだけで「衛生面に不安がある」と感じてしまい、DIY以前の問題として敬遠されます。一方で、キッチンは古くてもしっかり磨かれていると、それだけで「ここをDIYでおしゃれにできるかも」とポジティブな発想につながります。
質の低いDIYの悪影響を回避する
DIYの範囲を明確に制限する、DIYを行う前にオーナーの承認を得るというルールを設ける物件の安全性や清掃が整ったら、いよいよDIYの自由度について入居者と共有する段階に入ります。ここで最も重要なのは、DIYの範囲とルールを明確にすることです。このステップを怠ると、入居者によって思わぬ改装が施され、物件価値の低下やトラブルの原因となることもあります。
DIY賃貸の最大の特徴は「自由度の高さ」ですが、これはあくまで適切な範囲内でこそ活きるものです。たとえば、壁紙やペンキの塗り替えは入居者が自由にできる範囲ですが、構造に関わる柱や梁を変更する、電気配線をいじるなどの作業は、物件の安全性を損なう恐れがあり、明確に禁止すべき範囲です。
入居者がDIYできる範囲を明確にする
● OKな作業:
○ 壁紙の張り替え(既存の壁を傷つけない範囲で)
○ ペンキ塗り(養生をきちんと行い、他の設備に塗料がつかないように)
○ 棚や簡単な収納の取り付け(壁に穴を開ける場合は、補修可能な範囲)
○ 照明器具やカーテンレールの交換(電気工事士が不要な範囲)
● NGな作業:
○ 間仕切り壁の撤去・新設
○ 柱や梁など構造部分の変更
○ 配線・配管の工事
○ 法律上の資格が必要な工事(電気・ガス・水道の大規模変更)
このように、できること・できないことを明確に示すことで、入居者の自由度と物件価値の維持を両立できます。また、入居者がDIYを行う前には、オーナーへの事前申請・承認を必須とするルールを設けると安心です。これにより、施工の内容や材料、方法などを確認でき、予期しないトラブルを防ぐことができます。
原状回復義務の取り決め
DIY賃貸を成功させる上で、もう一つ大切なのが原状回復義務についての取り決めです。DIY可能な物件では、入居者が手を加えた部分をどこまで退去時に元に戻す必要があるかが、トラブルの火種になりがちです。この点をしっかり契約書に明記し、オーナーと入居者の認識を一致させておく必要があります。
また、DIY型賃貸用の特約付き契約書を作りましょう。ここで活用できるのが、国土交通省が作成した「DIY型賃貸借契約書」の雛形です。この契約書では、DIYの範囲や原状回復の義務、材料費や工事費の負担などがわかりやすく整理されています。この雛形をベースに、物件やオーナーの方針に合わせて調整し、双方が納得のいく契約内容を作り上げましょう。
https://www.mlit.go.jp/common/001228736.pdf
仲介を行う不動産会社に魅力を伝える
まずは、物件を扱ってくれる不動産仲介会社に、DIY可能物件であることの魅力をしっかり伝えましょう。DIY賃貸はまだメジャーなジャンルではありませんが、若年層やクリエイティブ層には確実にニーズがあります。そのため、物件の特徴を強調してもらうことが重要です。
近年は、InstagramやYouTubeを活用してDIY賃貸の実例を発信することで、入居者の関心を集める事例が増えています。たとえば、内装を手直しした事例を写真で紹介するビフォーアフター写真やペンキ塗りや棚の設置などの作業工程をYouTubeで公開するDIY動画「自分で作った理想の空間」などがあります。これらの発信は、DIYに興味がある入居希望者にとって、リアルなイメージが湧くため、反響を得やすいです。オーナー自身で発信できなくても、仲介会社に協力してもらい、SNSやWEBサイトで特集ページを設けてもらうのも効果的です。
まとめ
DIY賃貸が必ずしもすべての物件に適しているわけではありません。物件の立地や状態、地域の需要によっては、古家付きとして売却したほうが良いケースもあります。そうした判断には、不動産のプロによるアドバイスが重要です。
もし、空き家をどう活用すべきか悩んでいる場合は、ぜひ当社にご相談ください。地域の不動産市場に詳しいスタッフが、お客様のご希望や物件の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。賃貸か売却か、あるいはDIY賃貸という新たな選択肢か。プロの視点でしっかりとサポートいたします。

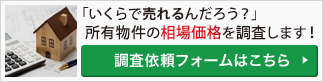
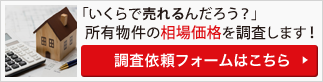








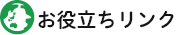

 不動産売却するならドットコム
不動産売却するならドットコム