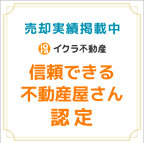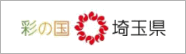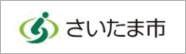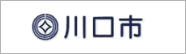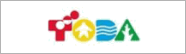平成27年に行われた相続税の改正によって、これまで課税対象とならなかった方々も相続税が発生する可能性が高くなりました。そうなってくると、やはり相続税をどうやって節税するかが大きなポイントです。せっかく財産を相続しても、相続税で損をしてしまうと元も子もありません。そこで今回は、税額を抑えられるかも知れない、相続税の控除についてご紹介します。
・相続税の基礎控除について
相続税には税額のかからない金額、つまり基礎控除額が定められています。平成27年の改正では基礎控除額に変更が加えられました。改正前と改正後の基礎控除額を比較してみましょう。
改正前(平成26年12月まで)の基礎控除額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後(平成27年1月から)の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
この改正によって、これまで相続税が一切かからなかった金額の相続についても、課税されるケースが生まれてきたのです。したがって、相続で損をしないためには、控除額を増やして課税金額を減らすことを考える必要があります。
・相続税の控除について
基礎控除のほか、活用したい特別控除をご紹介します。利用できるものがあれば、積極的に活用しましょう。
1)暦年課税方式
生前贈与も立派な相続税対策です。この暦年課税方式は、贈与によって取得した財産、年間110万円までは控除対象になります。10年にわたって定額の贈与を受けるなどすることで、相続財産を減らせるため、課税額も削減できます。ただし、相続発生の3年以内に行われた贈与は相続財産とみなされます。
2)相続時精算課税方式
60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子・孫へ2500万円まで生前贈与したとき、贈与税が控除される仕組みです。金額や回数の制限はありません。贈与財産が住宅資金の場合は、贈与者の年齢は問われないため、上手く活用したいところです。
3)住宅取得資金贈与
父母、祖父母から20以上の子・孫が居住するための家屋の取得のために、使う資金として贈与された金銭が1,500万円までは非課税となる方法です。平成31年6月30日までに契約した住宅の取得であることや、贈与を受けた年の翌年3月までに実際に居住していること、贈与された側の年間所得が2,000万円以下であることなど、要件があるため注意しましょう。
4)小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地を、一定の条件下で相続されると評価額を80%削減できます。
○土地の面積の上限は330平米
○配偶者の場合、面積要件を満たせば80%減額。
○被相続人と同居していた子の場合、相続申告期限までに当該土地を所有し、居住し続けること。
○被相続人と同居していない子の場合、相続申告期限までに当該土地を所有し、かつ相続3年以内に配偶者を含む自己の所有の家(持ち家)に居住していないこと。

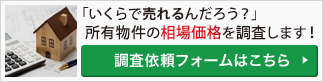
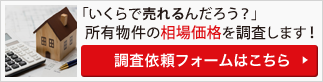









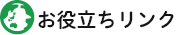

 不動産売却するならドットコム
不動産売却するならドットコム