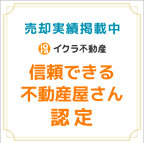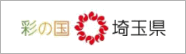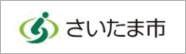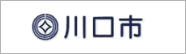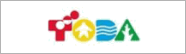2019/11/22

相続で亡くなった方の財産を引き継いだ場合には、所得税の申告も必要になることをご存知でしょうか。
亡くなった方が生命保険に加入していて死亡保険金を受け取った場合、手元の現金が増えたと喜ぶんだのもつかの間、所得税の対象になることもあります。
もし申告を忘れてしまったり、遅れてしまったりすると、税金を余計に負担しなければならなくなるかもしれません。
そのため、相続税だけでなく所得税についてもその内容を把握しておくようにしてください。
死亡保険金で現金が増えた場合は注意を
亡くなった方の財産を引き継いだ相続人は、財産の金額によっては相続税を納めることになります。さらにその一方で、所得税も納めることが必要になるのです。
相続に関連して所得税も発生するケースとは、亡くなった方が加入していた生命保険の死亡保険金を受け取った場合などです。
例えば、夫が妻を被保険者として生命保険の契約を行い、保険料を負担して受取人になっているなど、保険料負担者と保険金受取人が同じ場合が、所得税の申告・納税が必要になるケースです。
仮に自分を被保険者として生命保険に加入して保険料も負担しているけれど、受取人は子にしているという場合には相続税がかかりますし、被保険者と保険料負担者、受取人がそれぞれ異なる場合は贈与税の対象です。
準確定申告が必要になるケースもある
亡くなった方が個人事業主や年金受給者などで、毎年の所得税を確定申告で納めていた場合は準確定申告の手続きが必要です。
準確定申告は、相続が発生したことを知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から4か月以内に相続人が行います。ただし、亡くなった方の年金収入が400万円以下であり、年金以外の所得が年間20万円以下であれば準確定申告の必要はないとされています。
なお、年金収入だけで生活していた方が亡くなった場合、準確定申告を行えば源泉徴収されている税金の一部が還付されることもあるので、申告をしたほうがよい場合もあると理解しておきましょう。
準確定申告の対象となるのは?
準確定申告は、次のいずれかに該当する方が亡くなった場合、相続人が行うこととなります。
・個人事業主だった方
・アパートなど経営していて不動産所得のあった方
・給与の収入が年2千万円以上だった方
・生命保険や損害保険から一時金または満期金などを受け取った方
・医療費控除を適用させることが可能な方
相続税は一定額以上の財産を保有している方がなくなり、その財産を引き継ぐことになって発生する税金です。そのため、収入や財産が多い方は準確定申告が必要になることが多いので、抜かりのないよう申告を行いましょう。
準確定申告の期限を過ぎてしまうと無申告という扱いになり、追加で税金を払わなければならなくなるので注意してください。

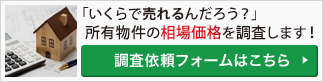
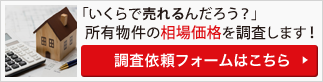



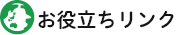

 不動産売却するならドットコム
不動産売却するならドットコム